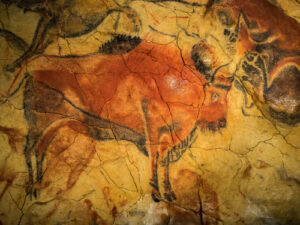マリア・テレジア(1717〜1780年)は、皇帝として即位しなかったものの「女帝」とされ、実質的には当時のハプスブルク家の広大な領土を統治しました。彼女は子宝に恵まれ、「ヨーロッパの義母」として18世紀のヨーロッパにおいて重要な存在として活躍。マリア・テレジアとはどういった人物だったのでしょうか?
今回はマリア・テレジアがどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、マリア・テレジアについて具体的に理解できること間違いなし!
マリア・テレジアとはどんな人物?
若い頃と夫フランツ1世との出会い

1717年にウィーンで誕生。父カール6世には男子がいなかったため、長女であった彼女はフランス北東部にあった小国・ロレーヌ公国の公爵の息子であるフランツ・シュテファン(後のフランツ1世)と1740年に結婚。当時としては珍しく、恋愛結婚とされていて、フランツ1世との間に16人の子供をもうけることになります。その後、カール6世は「プラグマティッシェ・ザンクティオン(国事詔書)」を制定し、娘が領土を相続できるようにし、彼女がオーストリア大公としてハプスブルク家が所有していたボヘミア・モラヴィア・ハンガリーなどの土地を相続。
しかし、女性の統治者だったため、カール6世の死後、ハプスブルク領の相続を巡り、プロイセン、フランス、バイエルンの周辺諸国などが、継承について反発(オーストリア継承戦争)します。プロイセン王フリードリヒ2世にシュレージエン(現在のポーランド南西部)を奪取されますが、最終的にハプスブルク家の領土の大部分を維持することには成功。
晩年と「ヨーロッパの義母」



1756年にプロイセンのフリードリヒ2世から奪われたシュレージエンの奪還を目指し、フランスやロシアと同盟(外交革命)を結びプロイセンと戦いますが、結局シュレージエンは取り戻せませんでした(七年戦争)。彼女は「啓蒙専制君主」の一人として考えられていて、官僚制度の整備や義務教育を確立したりと、近代化にも貢献しています。
そして、子供たちをヨーロッパ各国の王族と結婚させ、ハプスブルク家の影響力を拡大し、現在でもマリア・テレジアの血筋は各地で残っています。1765年には息子ヨーゼフ2世と共同統治となると、1772年にはポーランド分割に参加し、これに反対するも、オーストリア領を拡大。1780年に63歳で高熱により死去します。
マリア・テレジアにまつわる世界遺産はこちら!
シェーンブルン宮殿/オーストリア



ウィーン中心部から南西へ約7km。シェーンブルン宮殿は17世紀後半から20世紀初頭まで中央ヨーロッパを支配したハプスブルク家の居城だった場所。17世紀に神聖ローマ皇帝レオポルト1世(1640〜1705年)が夏の離宮の設計を依頼し、レオポルト1世の孫であるマリア・テレジアが家督を継承すると、宮殿を大改築して現在のように壮麗な宮殿に改築。
宮殿の外観はバロック様式で、装飾のほとんどがロココ様式。部屋の数はなんと1400を超えます。「百万の間」は中米の紫檀が使われ、ペルシアの細密画が飾られた豪華な部屋。謁見の間であり、公式行事などが行われた「鏡の間」は、幼いモーツァルトが演奏した部屋としても有名です。
詳細はこちら↓



世界遺産マニアの結論と感想
彼女は皇帝として即位することはありませんでしたが、政治の中心であったことから、実質的な「女帝」であり、教育改革により識字率向上し、中央集権化でオーストリアの国力は強化。しかし、2度の戦争においては敗退し、シュレージエンはプロイセンに奪われてしまいます。なんといっても子だくさんであり、娘にはフランスの王妃となったマリー・アントワネットだけではなく、現在もヨーロッパ各地に彼女の血筋は残っているという点では大きな功績でもありますね。
※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。