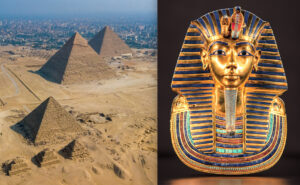二クラス・コペルニクス(1473〜1543年)は現在のポーランド出身の天文学者・数学者・経済学者・医者・聖職者であり、地動説を初めて唱えた科学者でもありました。後にガリレイやケプラー、ニュートンらに大いに影響を与えたことでも知られます。そんなコペルニクスとはどういった人物だったのでしょうか?
今回はコペルニクスがどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、コペルニクスについて具体的に理解できること間違いなし!
ニコラウス・コペルニクスとはどんな人物?何をした人?
「コペルニクス」とはどんな意味?

1473年に現在のポーランドのトルンに生まれ、父親は裕福な商人でした。しかし、父は早くに亡くなり、司祭であった母方の叔父ルーカス・ワチェンローデに育てられます。「コペルニクス」は、ゲルマン系の言葉で「銅」を意味し、さらにスラブ系の接尾辞で付けられもの。彼の父は銅を取り扱っていて、一族はドイツ系だったとされています。
1491年にクラクフ大学(現在のヤギェウォ大学)で天文学を学び、さらに1496年には叔父の支援を受け、イタリアのボローニャ大学へ留学し、法律を学びました。そして、天文学者ドメニコ・マリア・ノヴァーラ(1454〜1504年)の助手として観測を行い、地動説のヒントを得ることになります。
地動説の完成



ポーランドへと戻ってきたコペルニクスは、聖職者や医師としての仕事をしながら、天文学の研究を行います。この頃に地動説の着想を得て、彼は同人誌として『コメントラリウス』を執筆し、地動説の概要を身近な学者たちに発表。その後も天文観測を継続し、1529年ころから地動説の理論をまとめ始めました。
当時の惑星の位置の測定方法としては、プトレマイオス(83年頃 〜168年頃)の天動説(地球を宇宙の中心とする考え)を基盤としていましたが、彼はその考えに疑問を持ちました。彼は聖職者であったことから、太陰暦に従った復活祭の日にちの計算をするために研究を続け、毎年発生するズレに疑問を持ちます。その誤差から地球は不動の中心ではなく、他の惑星と同じく、太陽を中心に地球も動く天体の一つと考え、従来の世界観を覆しました。
地動説の発表と死因



彼はこの研究を世間に公表することはありませんでしたが、1542年に弟子から説得され、翌年に『天球の回転について』を発表。しかし、1542年にコペルニクスは脳卒中で倒れ、半身不随となってしまいます。彼は死の直前に本の完成を見たとされ、その後の地動説の行方を知ることがなく、世を去りました。
コペルニクスの理論は、直接的にはすぐに受け入れられなかったものの、ガリレオ・ガリレイの望遠鏡の観測、ヨハネス・ケプラーの楕円軌道の発見、アイザック・ニュートンの万有引力の法則など、近代物理学や天文学の基礎となりました。
コペルニクスとガリレオ・ガリレイの関係は?



ガリレオ・ガリレイ(1564〜1642年)は、イタリアの天文学者で、彼は望遠鏡を用いた天体観測を行い、コペルニクスの地動説を支持したことで知られています。しかし、彼は権力争いに巻き込まれ、敵を増やしてしまい、彼が支持した地動説を口実に異端審問を追求されました。
当時のカトリック教会は聖書に基づき「地球は宇宙の中心」と考えていたため、コペルニクスの死後すぐに批判されたわけではなく、ガリレオ・ガリレイの時代になって裁判が行われたことから、1616年に『天球の回転について』は禁書目録に指定されてしまいます。結局、ガリレオは有罪になってしまい、最終的に彼は地動説を放棄。死後も彼の執筆した『天文対話』も1822年まで禁書から撤回されませんでした。
ニコラウス・コペルニクスにまつわる世界遺産はこちら!
コペルニクスの生家/ポーランド



ポーランド中央部にあるトルンはヴィスワ川沿いにある交易で盛んな町でした。ドイツ騎士団の東方植民としてキリスト教が持ち込まれた後、ハンザ同盟に加わり、バルト海や東欧の国々と交易を行い、町は発展していきました。
旧市街には、ゴシック様式のファサードなどを持つ家が多く残りますが、その中でも有名なのは1473年にペルニクスが生まれたと伝えられている家。現在は博物館として保存されています。各家には貯蔵庫が設けられ、コペルニクスの生家も同様でした。
詳細はこちら↓



ヤギェウォ大学/ポーランド



クラクフは、ポーランド南部のヴィスワ川沿いに作られた街。ポーランド王国が築かれた11世紀になるとクラクフは首都となります。13世紀にモンゴル帝国軍によって徹底的に破壊されるもすぐに街は再建し、城壁で囲み、邸宅や宮殿、教会、修道院などの施設が多く造られました。
ヤギェウォ大学は1364年にポーランド王カジミェシュ3世により創建された大学。中央ヨーロッパで2番目に古い大学であり、コペルニクスの出身校でもあります。
詳細はこちら↓



世界遺産マニアの結論と感想
コペルニクスは、地球が宇宙の中心ではないという「地動説」を初めて本格的に提唱した科学者であり、彼の理論は現代の天文学の基盤となりました。 しかし、すぐに受け入れらませんでしたが、後のガリレオやケプラーらによって証明され、ニュートンの万有引力の発見へと繋がったことから、彼の研究は天文学だけでなく、科学革命を引き起こしたという点で偉大な人物でもあるのです。
※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。