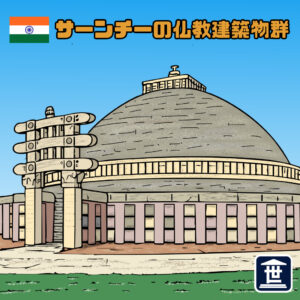アショーカ王(在位:紀元前268年頃〜紀元前232年頃)は、マウリヤ朝の第3代の王であり、インド亜大陸を初めて統一した偉大なる王です。そして、初期仏教の庇護者として歴史に名を残しました。そんなアショーカ王とはどういった人物だったのでしょうか?
今回はアショーカ王がどんな人物だったかを世界遺産マニアが分かりやすく解説。これを読めば、アショーカ王について具体的に理解できること間違いなし!
アショーカ王とはどんな人物?

アショーカ王はマウリヤ朝(紀元前322年〜紀元前185年)の王であり、マウリヤ朝はもともとガンジス川の下流域に存在したマガダ国出身の開祖・チャンドラグプタ(在位:紀元前340年頃〜紀元前298年頃)によって建国され、後に東はガンジス川流域、西はインダス川流域、中央インドの一部を含む、巨大帝国となっていきます。
チャンドラグプタの孫であるアショーカ王は紀元前268年頃に即位し、南方のカリンガ国への遠征を行い、この地方を征服すると、マウリヤ朝の領土を最大範囲まで拡大しました。
しかし、その戦争で多くの人々が命を落としたことに心を痛め、仏教に深く傾倒するようになったとされています。彼は釈迦が解脱したとされるブッダガヤを訪れ、暴力を否定し、ダルマ(法)に基づく統治を目指すようになりました。そして、仏教を深く信仰したことでも有名ですが、異なる信仰の人々にも敬意を払い、やがて仏教がアジアに広く広まるきっかけともなったのです。しかし、晩年の記録はあまりなく、彼自身は地位を終われ、幽閉されたという説もあり、アショーカ王以降のマウリヤ朝は衰退していきました。
アショーカ王の石柱碑とは?



アショーカ王はインド各地に石柱を多く築いたことで有名で、それらはプラークリット(インド北部で話されていた、俗語的なインド・アーリア諸語)で碑文が刻まれたもの。柱の高さは12〜15mほどで、刻まれているのはダルマや仏教、王の施策、他の宗教への寛容などをテーマとしたもの。しかし、これらは19世紀まで解読されることがなかったのですが、古代インドの政治・宗教・社会政策の記録がされていることもあり、貴重な資料となりました。
仏教の四大聖地の一つであるサールナートの石柱は、かつて飾されたいて四頭の獅子の柱頭を持ち、これをもとに現在のインドの国章はデザインされています。
アショーカ王にまつわる世界遺産はこちら!
仏陀の生誕地ルンビニ/ネパール



ルンビニは、ネパール南部のテライ平原に位置する小さな村。ここは釈迦の生まれた地として知られますが、生誕の時期は諸説あり、紀元前7世紀〜紀元前5世紀ころとされています。
そして、聖地とされたのは、紀元前4世紀〜紀元前2世紀ころにインドの統一王朝であったマウリヤ朝のアショーカ王によって、紀元前249年に釈迦の生誕地を示す石柱が築かれたことから。
詳細はこちら↓



ブッダガヤの大菩提寺/インド



ブッダガヤは、ビハール州パトナから約100kmの距離に位置し、釈迦が菩提樹の下で悟りを開いた地とされています。ここは仏教の4大聖地の1つで最も重要な聖地。この地にある大菩提寺(だいぼだいじ)はマハーボディ寺院とも呼ばれます。
マハーボディ寺院は、もともとは紀元前3世紀にインドで栄えたマウリヤ朝のアショーカ王によって建てられた仏教寺院を起源となっています。現在の寺院は5〜6世紀に建てられたものがベース。
詳細はこちら↓



サーンチーの仏教建築物群/インド



サーンチーは、インド中部マディヤ・プラデーシュ州のボーパールから北東へ約40km離れた仏教遺跡。ここは3つのストゥーパと祠堂、僧院などが点在しています。
彼は特にここを重要視していて、8つのストゥーパを建造したと伝えられますが、現在は3つのストゥーパが残存。他にも多数の祠堂や僧院の遺跡が残り、12世紀まで聖地として栄えました。
詳細はこちら↓



世界遺産マニアの結論と感想
アショーカ王は、古代インドでも最大の征服者であったものの、戦争の悲惨さから仏教を守護し、結果として仏教を広めた王へと転身しました。実際はどれだけ効果はあったかは不明ではありますが、彼は法による政治を行い、後世に大きな影響を与えたという点でも先進的な王であったとも考えられますね。
※こちらの内容は、世界遺産マニアの調査によって導き出した考察です。データに関しては媒体によって解釈が異なるので、その点はご了承下さい。